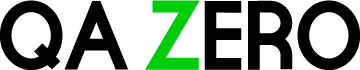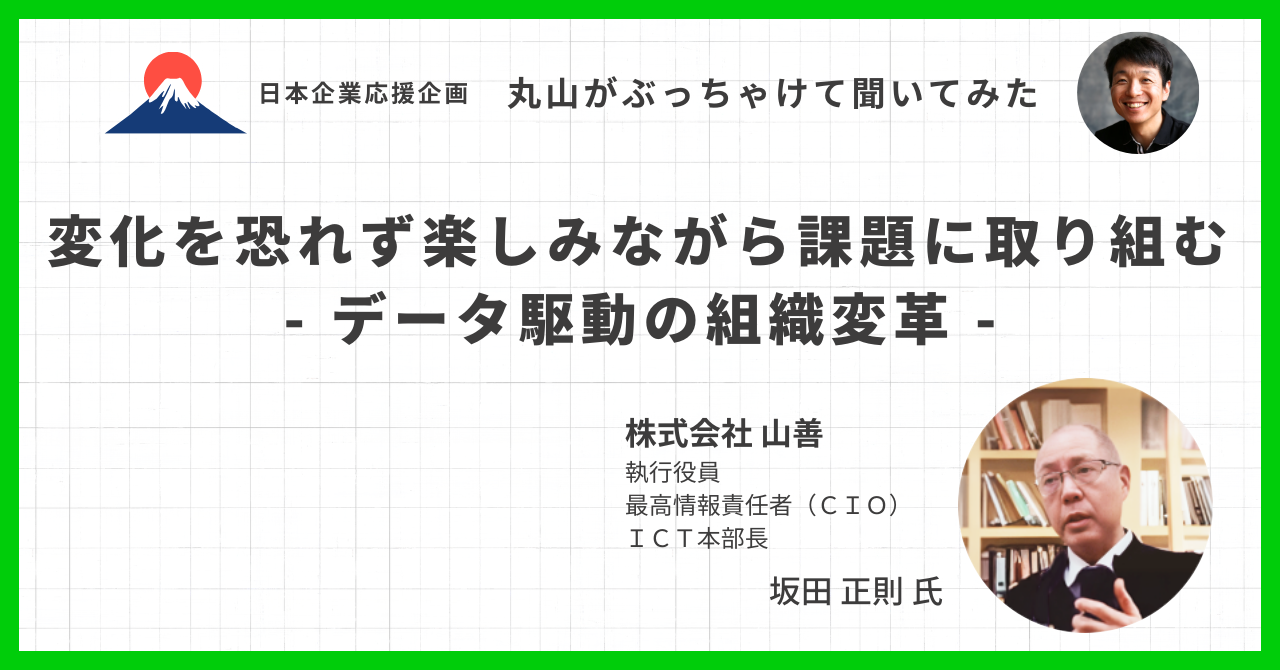日本企業応援企画として、「データ活用への取り組み」についてさまざまな日本企業の方と丸山が対談しています。今回は、株式会社山善・CIO(最高情報責任者)兼ICT本部長の坂田正則さん。山善様では、お客様のニーズを理解し価値を提供するという重要課題に対し、デジタル・データ活用推進を進めていらっしゃいます。今回の対談では、山善社内のDX戦略やデータ活用、お客様へのデジタル面での支援など、現在取り組まれていること、推進活動の中で出てきた課題など、ぶっちゃけて坂田さんに丸山がお聞きしました。
山善は、生産現場で使われる工作機械、産業機器、機械工具、自動化ロボットなど、世界のものづくりを支える「生産財」と、快適で便利な住まい・オフィス環境をつくる住宅設備機器・建材や、くらしを豊かに彩る生活用品などの「消費財」を提供する専門商社です。
坂田 正則 氏
株式会社 山善 執行役員 最高情報責任者(CIO) ICT本部長
山善におけるCIOの役割と組織づくり
変化を楽しむ人が組織を動かす

本日はよろしくお願いします。
坂田さんは早い段階から、山善さんのデジタル分野においていろんなことに取り組まれていますよね。経験も豊富ですし、ご自身でもかなり勉強されている印象です。その原動力はどこから来るんでしょうか?

好奇心でしかないと思いますね。仕事や今やっていること、これからやることに興味を持って取り組む、ということが一番大事ではないかと考えています。
自分自身、このポジションに着いたときから、考えたり勉強し始めたりしたこともたくさんあります。この歳から「数学やる」ってなかなかの負担もありましたが(笑)
でも面白いところを見つけて、自分なりのモチベーションをあげて取り組んでいることも多いですね。

だからこそ、社員にも「面白さとか楽しさを提供する」というのが大事かな、と思っています。スピードをあげるためにもね。
わからないから外注や人に丸投げするというのがそもそも好きではありません。誰しも最初は素人。自分なりに勉強して解決策を見出して実行してみて、そこで「面白いな」って乗り越えていかないとなかなか次のステップにはいけない。
面白さや楽しさが感じられる環境をまず整えている、というところですね。
CIOの役割と組織づくり

変化を楽しむ姿勢が原動力になる。
坂田さんのお話を聞いて、それがそのままCIOとしての仕事のあり方にもつながっていると感じました。では、CIOとして実際にどのような取り組みをされているのでしょうか?

CIOとしての現在の取り組みは、端的に言うと「ITガバナンス」です。
つまり、適切なIT戦略を立案し、それを遂行するための体制や仕組みを整えること。
それに加えて、予算の管理や投資対効果の管理も含めて、最終的には会社の収益に貢献する活動を行っていくこと、そのための組織や体制を作っていくことが、今の取り組みです。

特に注力されていることはありますか?

データ分析の基盤の拡充と、その活用ですね。
山善は商社、商社とは商売人の集まりですから、結局財産は「人」です。人を、自分をどれだけ売り込めるか、というのが一つの勝負といった側面を持っています。
お客様とたくさん対話して、情報を集めて、提案を繰り返す。その中で成功もあれば失敗もあって、そうした経験を積み重ね、横に広げていくことで会社は成長してきました。
取引のサプライチェーンを効率化することも大事ですが、本当に大事なのはお客様の問題解決につながるような人の付加価値をどう作っていくかという点です。
そのためには、「人の、営業の、能力を拡張するデータ作り、データのインプットから、アウトプット(データ分析)、教育までを一貫した仕組み」とする必要があると考え、関連する機能部署を統轄する組織として「ICT(Information & Communication Technology)本部」を立ち上げました。
山善のデジタル活用とは
中小企業のお客様に果たしたい役割

CIOとしての取り組みが、「人を軸とした組織の変革」と「お客様の課題解決」という2つのテーマに貫かれていることがよく分かりました。
デジタル化やDX推進と言えば、つい大企業の取り組みを思い浮かべがちですが、中小企業にも現実的な課題は多くありますよね。お客様の課題を解決する取り組みについて具体的なお話をお伺いできますか?

たとえば、生産財事業での我々のお客様は中小企業が多いです。
中小企業の方は、なかなか自社だけでデジタル化を推進するのは難しいです。

なるほど。人手不足もありますしね。

面白さや楽しさがあると営業提案の質もスピードも向上、失敗も前向きに

中小企業の課題に対して、現場に寄り添ったデジタル化の支援を実践されているんですね。
ではそれを支える山善さんの営業のあり方も変わってきているように思いますが、どう変化しているのでしょうか?

さきほどもお話しましたが、デジタルツールを使うこと自体が目的ではなくて、やはりお客様の課題解決にいち早くつなげるために活用するものだと捉えています。

それがまさに、価値提供につながるということですね。

そうなのですが、そうとも限らない。たとえば、「我々はこういう価値を提供している」と思っていても、実際にお客様がどう感じているかは分からない。
だからこそ、仮説を立てて、それをデータで検証するというプロセスが必要です。
もともと我々の営業スタイルは、とにかくお客様のところにたくさん訪問して、たくさんの人と話して、たくさん情報を集める。そうやって関係性を築き、ニーズを掴み、事例を積み重ねていく。これが当社の強みでもありました。
ただその営業スタイルは属人的になりがちです。「KKD」と言われるような、個人の勘と経験と度胸でやっていたところが大きいです。
担当者が変わったらゼロからやり直しになってしまう。会社としての継続性がない。
だから、そこに「データ」が必要なのです。
属人的なやり方から、再現可能なデータ活用型の提案に変えていく。そのための土台を今作っています。

仮説検証を通じて、価値の再定義をしていくようなプロセスですね。

営業現場の経験や知見を、きちんと記録して、分析して、組織全体で共有する。そうすることで、再現性のある提案ができるようになりますし、スピードも精度も上がる。
最終的にはお客様の満足度も上がっていくと信じて、今は全社的に取り組んでいます。

確かに、経験だけでは属人的になってしまいますし、組織としての価値提供には限界がありますよね。

まさにそうです。
対面営業はどうしても感覚に頼りがちになりますが、それを適切に記録しておくことで、次に活かせると考えています。
たとえば、「どういう商品が評価されたのか」とか、「お客様がどういう言葉に反応したか」とか、「なぜ上手くいかなかったのか」とか、そういった情報を残していく。
それが次の営業活動の質を上げる材料になっていきます。

経験だけに頼らず、再現性を持たせていくという点で、データの役割は大きいですね。

そうですね。
さらに価値というのは、我々が決めるものではなくて、お客様が決めるものだと思っています。
だから、お客様に「ありがたい」「助かった」と思ってもらえるような行動が取れているのか。
それを振り返るためにも、データは重要な手段になってきます。
それに、仮説を立てて検証して、「やっぱりそうだった」「ちょっと違ったね」ってやっていくプロセス自体が、やってみると面白いです。
面白さや楽しさがあると、提案のスピードも上がるし、失敗しても前向きに捉えられる。
データ活用って単に効率化や正確性のためだけじゃなくて、「考えることを楽しむ」ための手段にもなると思っています。
データ基盤の整備と人材育成
データ分析とは、提案とニーズのギャップを埋めていく作業である

価値は「お客様が決めるもの」というお話、もう少し詳しくお聞きしてもいいですか?

我々自身の収益はお客様からいただいていて、それはお客様に価値を認めていただいているからこそ生まれるものです。
我々が良ければいいという話ではなく、お客様に価値を感じていただくことがとても大事です。
山善に対してお客様が感じている価値は何か?と考えてみると、いろいろな要素があると思います。
商品がいいというのも一つでしょうし、品揃えがいい、納期が早い、情報提供してくれる、相談に乗ってくれる。
そういった複合的な要素があります。
その中で我々がデータを活用するというのは、「その価値って何なのか?」をもう一回捉え直すことから始まると私は思っています。

なるほど。顧客に提供していく価値というのは、商品そのものだけではなくて、それ以外の部分も含めて複合的なものなんですね。

繰り返しになりますが、「自分たちはこういう価値を提供している」と思っていても、実際にお客様がどう思っているかはわからない。
そこをちゃんとデータで確認・分析していく。仮説を立てて検証していく。
そういうやり方が、今の時代には必要だと思っています。
そして最終的には、お客様の課題を100%解決することにどこまで近づけるか。
それこそが本当に大事なことだと思っています。

データの使い方についてもお聞きしたいのですが、どのように分析を捉えられているのでしょうか?

分析は、あくまで「手段」だと思っています。
目的はお客様の課題を解決することであり、お客様に価値を感じていただくこと。
そのために「こういうことができるんじゃないか?」という仮説を立てて、実際にデータで検証していく。
データ分析は「お客様のニーズに対して、自分たちの提案がどれだけ近づけているか」を確認するためのプロセスだと、私は考えています。
あくまで「価値を判断するのはお客様」です。
私たちが「これが正しい」と思っていても、それが本当にお客様に求められているかどうか。これがズレていたら意味がありません。
だから私は、「データ分析とは、提案とニーズのギャップを埋めていく作業である」だと捉えています。
面白さは武器になる。データ人材を育てるには

「再現性のある営業」や「価値の再定義」など現場でデータ活用して、となると実践するには「データ人材」が必要になりますね。

そうですね。昔は「情報を持っていること自体が強み」でしたが、今は「情報をどう使うか」が問われる時代になってきました。
一方で、今の時代は情報が逆にあふれかえっています。
本当に必要な情報を見つけて、適切に使いこなせるかどうかが重要です。
“使える人”と“使えない人”の間で格差が拡がっている。
私は、それが今の時代の一番大きな課題の一つじゃないかと考えています。
つまり、情報が手に入るかどうかの勝負ではなくて、「どう料理するか」の勝負です。

情報の価値が「持つこと」から「使いこなすこと」へと変わってきている中で、それを活かせる人とそうでない人の差が開いているというのは、現場でも実感しますね。
その「料理する力」を育てるために、坂田さんはどのようなスキルや環境づくりを重視されていますか?

そのために必要なのが、情報リテラシー。情報を選び取って、整理して、判断につなげていく能力がなければ、データを持っていても宝の持ち腐れになってしまいます。

そうなるとデータ人材育成がより重要になってきますよね。

おっしゃる通りです。我々も、どうやってデータを使える人材を増やすかということを意識しています。
たとえば研修をしても、座学で聞いているだけじゃ身につきません。
実際の業務の中で、「このデータってこういうふうに役立つんだ」って体感することが大切です。
実践ベースで「仮説を立ててデータを見て提案してみる」。
そういう経験を積む機会を意識的に作っています。
うまくいけば「これは面白い」となりますし、成功体験が共有されれば、組織としての学びにもなる。
最初の一歩をどう作るかが鍵だと考えています。

いわゆる「データを扱える人」を育てるというよりは、「まずは興味を持つ人」を増やすことがスタート、という感じですね。

まさにそうです。
全員が分析の専門家になる必要はありません。
データに興味を持って、使ってみようと思える人を少しでも増やしていきたい、と考えています。
やってみて「面白いな」と思えると、そこからどんどん深掘りしていけます。
実際に私たちDXのチームにおいても、「このデータを見ていたら面白くて、気づいたら1時間経ってた」みたいなこともあります(笑)。
やはり興味や楽しさが入り口になるんだと思います。それが結果的に、社内の文化としても広がっていくと考えています。

データを活用できる人材を育てるには、まず「面白さ」や「興味」が重要だというお話が印象的でした。

興味や楽しさ、面白さがないと続かないですからね。社内の文化づくりも含めて、データを扱える基盤整備を進めています。
データが使えるだけでなく、それが現場の意思決定や行動につながることが大事です。
まずは「使ってみる」ことから始め、成功体験を社内に共有する。
それが他部門への波及効果を生み、少しずつ会社全体の変化を促していくと考えています。
外部パートナーとの協力や連携は重要

実際に、今のような仕組みや文化を社内に根づかせていくにあたっては、外部のパートナーやベンダーさんとの連携も重要になってくると思うのですが、そのあたりはどうお考えですか?

おっしゃるとおりで、やはり社内だけで全部をやるのは難しい部分があります。
我々のような企業がすべて内製でやるには限界があって、スピードの面でも専門性の面でも、外部のパートナーにお願いする必要があります。
ただ、そのときに大事なのが「山善のことをどれほど理解していただいているか(理解しようとしているか)」と「どうコミュニケーションをとるか」なんです。

たとえば「この機能を作ってください」と依頼するだけでは、なかなかうまくいかないケースが多いです。
ベンダーさん側からすれば「要件通り作ればいい」となってしまいがちですが、それだとこちらの本当の目的が伝わらないこともあります。
戦略的な内容や「最終的にこの機能がどういう目的につながるのか」という視点で話していくと、プロジェクトの動きが変わってきます。
要するに「目的や目標を共有できているかどうか」が、そのプロジェクトがうまくいくかどうかに関係してくると感じています。

目的や目標のズレは、プロジェクトを推進する上でかなり重要な問題ですよね。

はい。ベンダーさんにお願いするときも「こういう背景で、こういうことを達成したいから、この仕組みが必要です」というところまで、丁寧に伝えるようにしています。
それがあると、ベンダーさんのほうから「それであればこういうやり方のほうが良いのでは?」と提案してくれることもある。
このように進めることで、より良いものができます。

あと我々の側にも「伴走できる人」が必要です。
ただベンダーさんにお願いして終わりではなくて、一緒に考えられる人、自分たちの中で責任を持って動ける人がいるかどうかもとても重要だと感じています。
海外展開への展望
「人を介して価値を届ける」専門商社の強みと海外展開

ここまで国内での取り組みやデータ活用、人材育成など多くのお話を伺ってきましたが、山善さんの取り組みは国内にとどまらず、海外にも展開できそうな印象を受けます。グローバル展開について、どのようにお考えでしょうか?

経営的な観点から言うと、海外に活動の場を見出していかないといけないと考えています。日本市場だけに依存できないという危機感があります。
日本国内の市場をみても、機械や製品の使用タイミングやニーズがどんどん進化・変化しています。この進化に対応するには、海外市場の可能性をしっかり捉えていく必要があると思っています。

今まで国内で使っていたものや、社内で蓄積してきた仕組み・ノウハウって、実は海外でも十分に通用し展開できる可能性があるのではないか、という手応えも感じています。

なるほど。それはすごくポジティブな視点ですね。既にある資産をベースに、グローバルでも再現できるのではということですね。

はい。もちろん各国の市場環境や文化、商習慣の違いはあります。
山善は商社として「人を介して価値を届ける」ビジネスモデルを持っていますので、それをベースにして、現地の事情に合わせながら展開していくことができるはずです。
海外展開では、「機能的なものを備えているか」「本当に必要とされるものを届けられるか」といった点が特に重視されます。
そのためには、日本で積み上げてきた価値提供のやり方をベースにしつつも、ローカルにフィットさせていくことが大切になります。

それこそ、現場での「人間力」が問われる部分ですね。海外における商社の存在って、単なるモノのやり取りにとどまらず、信頼関係や理解力も含めた総合力が試されるイメージがあります。

そうです。どこの国でも、結局は「この人と仕事がしたいかどうか」がとても大事です。
そこに我々の存在価値があると信じています。
データ活用の本質
データ活用の本質とは?仮説で動く組織へ

これまでのお話からも、坂田さんが「データ分析はあくまで手段であって、目的ではない」という姿勢を大切にされていることがよく伝わってきました。その点について、改めてお聞かせいただけますか?

はい。データ分析自体が目的になってしまってはいけないと常に考えています。
「このデータを見てこうでした」というのはもちろん大事です。
それで「だから何が言いたいのか」「それでどうしたいのか」っていうのがなければ、意味がないと思っています。

つまり、計画や仮説を立てて検証するというプロセスが重要で、「お客様が本当はこういうことに困っているんじゃないか」とか「こういう視点で提案すればもっと喜んでもらえるんじゃないか」というふうに、自分たちで計画や仮説を立てて、それをもとにデータを見る。
仮説を実行してうまくいったかどうかを確かめて、また次に活かすというサイクルが必要です。

分析の結果を見て終わり、ではなくて、その先のアクションにどうつなげるかが大事ということですね。

そうです。だから、分析の結果だけで満足して「よかったね」で終わるのではなくて、「じゃあ次にどう動くか」というところまでを含めて考える。
それが「手段としてのデータ活用」だと思っています。

「三方よし」という言葉がありますが、売り手よし、買い手よし、世間よし、と言われる近江商人の言葉で、売り手側も買い手側も満足する形で、社会全体の満足を追求しましょうという考え方ですね。
誰かの問題解決が、また別の誰かの役に立って、それが広がると社会全体の貢献にもつながっていく、という風に思っています。

まさに三方よしの考え方ですね。

そうですね。目の前のお客様の問題解決がもちろん一番大切です。
一方で、今般リリースしたものづくり研究所(製造業向けお役立ちサイト)を使って、インタラクティブに情報発信や情報共有する機会を増やしていけば、もっと広く循環していける可能性があると考えています。

なるほど。これはマーケティングに活かせる考え方ですね。

そして、データを見て判断するというのは、別に特別なことじゃないとも思っています。
「データ分析」と聞くと、特殊な仕事のように感じる人は多いです。でも「お客様が困っていることを解決するためにどんな手段があるか」と考えると、自ずと導かれることだと思います。
「営業現場で起きていることの背景には、こういうことがあるんじゃないか」とか、「あのお客様は以前こう言っていたから、もしかしたらこういうニーズがあるかもしれない」とか。
このような仮説は、実は営業や現場の人たちは普段から持っていると思います。
それを言語化して、データと紐づけて確認する。
その流れを、もっと自然なかたちで日常に組み込んでいけたらと思っています。
興味をもつ・楽しむ・面白がる

ここまでお話を伺っていて、坂田さんの中には「変化を楽しむ」「面白さを見出す」という姿勢が強く根づいているように感じます。その考え方について、最後に詳しくお聞かせいただけますか?

私が大事にしているのは、「仕事は面白いものだ」と思って興味をもってやることです。「面白さ」がないと続かないと思います。
これまでにも「このプロジェクト、まだまだ面白さを見出せてないな」と感じる場面もありました。だからこそ「どうすれば面白くなるか」を考えるんです。
そうやって取り組む姿勢を変えていくと、だんだんプロジェクトに対して前向きになれます。

おぉー。難しいことですけど分かります。

最近ではAIの活用も進めていますが、これも面白いです。たとえば「どういうシナリオでこういう回答をしてほしいから、こんな風にプロンプト作ろう」とか、「このデータとこの情報をつないでいけば、もっと良いアウトプットが得られるかも」って考える。
プロンプト作成の過程が、創造的で面白い。知的な作業として楽しんでいます。
一方で、もちろんリスクもあります。AIに頼りすぎることで、「人が考えなくなる」という可能性はあると思っています。
でも、それを理解したうえで「どう付き合っていくか」を考えるのが大事だと考えています。

プロンプトの設計自体が、思考のトレーニングみたいなものですよね。

そうそう。遊び心もあって実用性もあって楽しいです。
こういう「楽しみながら付き合える技術」が出てくると、変化そのものが面白くなりますし、仕事の幅も広がっていきます。そういう意味でも、今はすごくいい時代だと感じています。
最終的に「変化を楽しめるかどうか」「面白がれるかどうか」「興味を持てるかどうか」が、その人自身の成長にも、組織全体の変化にも直結していくと考えています。

今回むちゃくちゃ深い話でした。ありがとうございました。
DXはホットキーワードですが、マーケティング視点というか「そもそも自分たちの商売が何なのか」っていう視点からデータを見る、っていう文脈で語られるコンテンツって実は少ないんですよ。

サプライチェーンDXとか、業務の見える化とかは、もちろん大事です。
そこから課題があれば改善することも大事、そのためにデータを活用することも大事。でも、それって仕事を進める上で当たり前のことですよね。
そこからもう一歩踏み込んで、データを使ってどうやって付加価値を生んでいくか、お客様や社員に喜んでもらえるかということが私なりのテーマであり、これからも進めていきたいことですね。
対談を終えて
坂田さんをはじめ山善さんとは、これまで約2年のお付き合いがありますが、今回のように坂田さんご自身の考えをじっくりお聞きするのは初めてでした。対談の1時間はあっという間で、大変濃密な時間となりました。
事前には、経験も知識も豊富な坂田さんのことですから、少し技術寄りのデータ活用の話になるかもしれないと思っていました。しかし実際に始まってみると、話は想像とはまったく異なる方向へ進みました。むしろ、「与えられた中で、自分はどう生きるのか?」という、ある種の禅問答のような根源的な視点から、データをどう活用するかというテーマが展開されていったのです。
多くの日本企業では、データ活用やDXといえば「導入すべき仕組み」として捉えられがちです。そうした中で、坂田さんの視点は一貫して「お客様のニーズを見つけ出し、応えることこそが商売の本質であり、データはそのために使われるべきものだ」というものでした。まさに、海外の先進的なDX事例でも見かけるような、本質を突いた考え方だと感じました。
さらに印象的だったのは、「山善らしく社員が活動できるよう整備していくことが、自分の役割だ」と語られていたことです。ICT本部やDX部門に限らず、社員一人ひとりがデータ活用に興味を持ち、それを通じてお客様に提供できる価値を高めていく。坂田さんはそのための環境づくりを、長期的な視点で着実に進めておられるのだと感じました。
経営層の立場でここまで現場と人に目を向け、丁寧に言葉を紡がれる姿勢に、改めて尊敬の念を抱きました。今回の対談でお話しいただいたことに、心から感謝いたします。坂田さん、本当にありがとうございました。