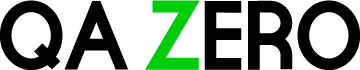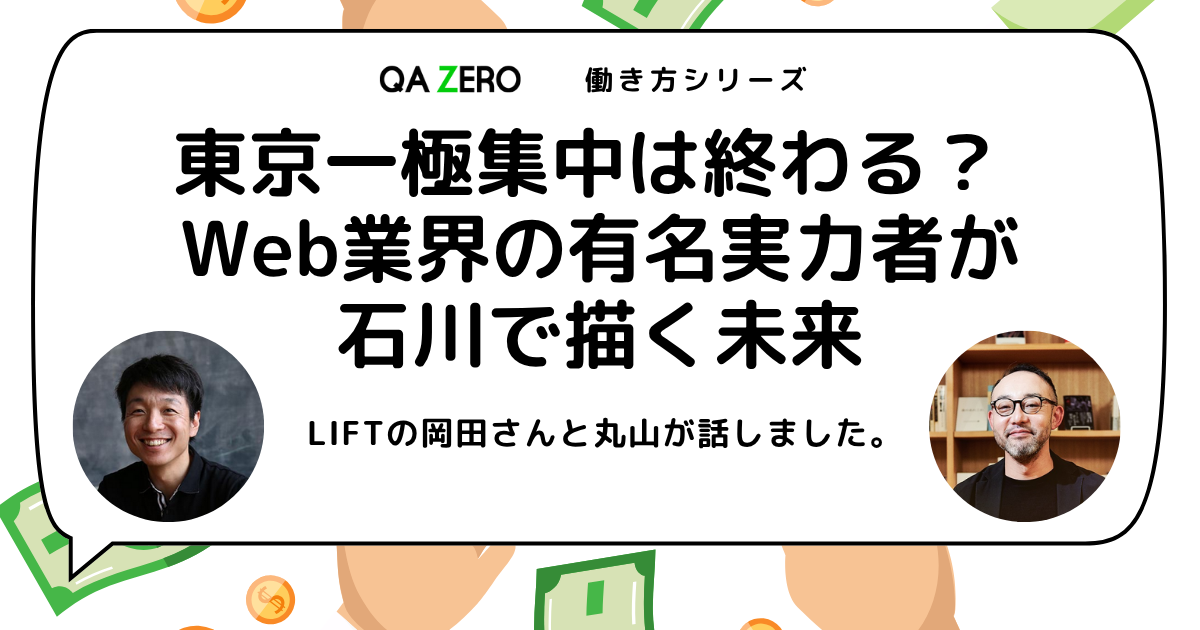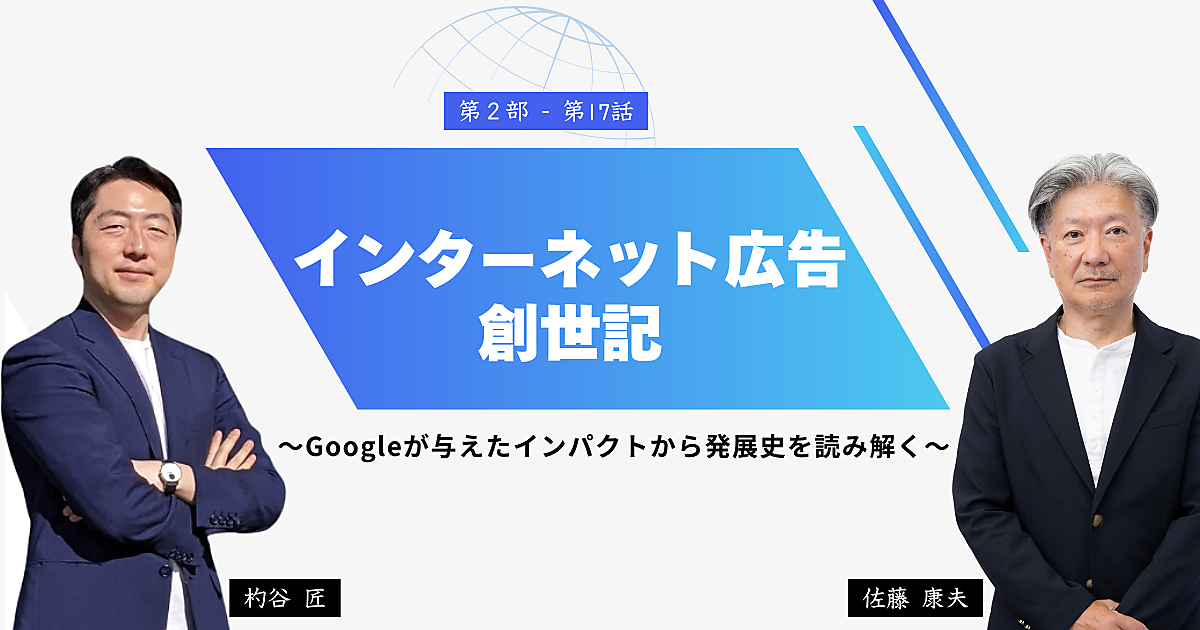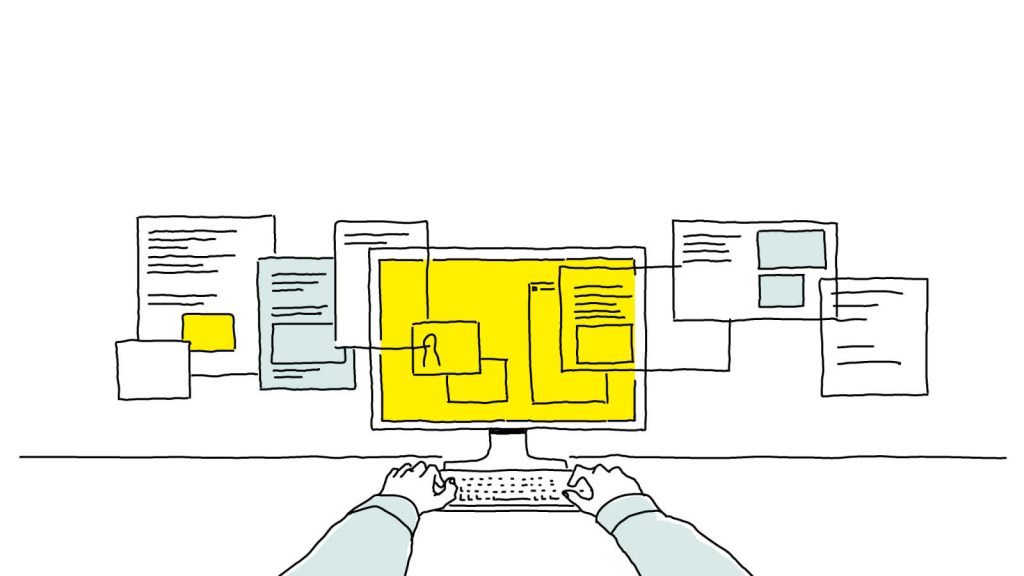私たちQA ZEROはデータを通じて、AI時代に人の創造性を支援するツールとして開発を続けています。今回はそんなAI時代の人の創造的な働き方の探求の一環として、前回のYuwai田中さんに引き続き、第二弾として広告業界の第一人者で有名なLIFT合同会社の岡田さんにインタビューを行いました。
東京の名だたる企業で上場、M&A、会社の代表取締役などを経験された今、石川県金沢に移住された背景や今後の展望について伺います。お聞きしてわかったのは、意外にも劣等感から始まったというキャリア初期について、また現代における地方の可能性。
東京と地方の格差に悲観的だった丸山にとって、目から鱗だった「創造的な働き方」のお話しをぜひお読みください。
LIFT合同会社 代表取締役 岡田吉弘(オカダ ヨシヒロ)
広告代理店、GoogleにてSEM黎明期から一貫してアカウントマネジメントの現場を主導し、最大手からスタートアップまで幅広く運用型広告の啓蒙・拡販に従事。アタラ合同会社、アナグラム株式会社、フィードフォースグループ株式会社、株式会社リワイア等の役員を経て、現職。
連載
著書
目次
第一章:まさかの劣等感からはじまった。驚きのキャリア初期

本日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうございます。まずは岡田さんのキャリアの初期について詳しくお伺いしたいと思っています。最初から広告分野に入られたのでしょうか?

こちらこそありがとうございます。広告に足を踏み入れたのは2社目からで、新卒ではSIer(システムインテグレーター)に入りまして、メインフレームのCOBOLプログラミングを担当していました。

COBOLプログラミングですか!Web業界の第一人者というイメージからは、少し意外なキャリアスタートですね。私もSIer出身なので妙な親近感です笑。プログラミングのご経験は当時からあったのでしょうか?

それが全くなかったんです(笑)。就職氷河期で就職先がなかなか見つからず、採用していただけたのがSIerだったという状況でした。ですのでエンジニアと呼べるようなキャリアではありません。

なるほど、そういった背景があったのですね。ものすごく意外です。

最初のプロジェクトでは、大手さんの銀行などの勘定系のシステムに携わらせていただきました。ただ、メインフレームからクライアントサーバーに移行していくという時期で、COBOLを書きながらも、徐々に新しい技術に触れるような形でした。ただプログラムも経験がなかったですし、最初にアサインされたプロジェクトでも、もうボコボコにやられてしまって。「俺は本当にダメだ」と、プライドなんて全くなくなりましたね。
Web業界に入るきかっけ

金融システムのエンジニアってだいぶWebと遠い状況ですよね。特に2000年代となるとなおさら。そこから、どのようにしてWeb業界に興味を持つようになったのでしょうか?

どん底を味わっていた時に、フロントエンドの画面を作るという業務を任されたんです。COBOLなどのバックエンドの処理とは違い、ユーザーが見る部分を作る仕事だったのですが、それが初めて仕事で褒められた経験だったんです。

初めて褒められた、ですか。たしかにUIの仕事ってSIerの中でも特殊ですよね。

ええ。「こんなに綺麗に作ってくれるとは思わなかった」と言っていただけて、もしかしたら、構造を理解した上でエンドユーザー側に行く方が向いているのかもしれない、とぼんやりと思いました。実際は単に私への期待値が低かったので多少まともなものを出した意外性で褒められただけなんですが、初めて褒められたのがその仕事だったので、「じゃあそっちへ行ってみようかな」と。単純なので(笑)

そこからWebの道へ進むことを考え始めたのですね。

はい。それがきっかけで、HTMLやスタイルシート、JavaScriptといったフロント側の技術を少しずつ勉強し始めました。HTMLはタグなので、複雑ではないですから、作っていくうちにだんだん面白くなっていったんです。

独学でWebの技術を習得されたのですね。

勉強のためにWeb系の雑誌を定期購読していたのですが、その中に当時、Google Japanのトップだった佐藤康夫さんという方が誌面に登場されていて(※)、初めてWebのアクセスアップ、つまりSEOというものを知りました。それが2002年頃だったと思います。それまでは、ただWebサイトを作ることに満足していたのですが、SEOを知ったことで、多くの人に見てもらうための技術があるということに衝撃を受けました。それが、私がWebの世界に深く足を踏み入れる大きなきっかけになったと言えます。
(※)当時の雰囲気がウェブ担当者フォーラムさんの記事でわかります。貴重な資料ですね。
第二章:まるでジェットコースター。ベンチャー、IPO、そしてGoogleへ

2002年というと、かなり早い時期にSEOに出会われたのですね!

その後転職を考えて、最初に内定をいただいた何社かの中で、いちばん規模の小さかったベンチャー企業を選びました。当時はまだ10名くらいで、SEOコンサルタントとして入社したのですが、本当にジェットコースターのような目まぐるしい経験をすることになりました。

どのような状況だったのでしょうか?

入社時は10人程度の会社でしたが、退職する3年後頃には50人ほどの規模になっていました。売上も数億円から数十億円規模へと急成長してIPOまで行きましたので、本当に目まぐるしく濃密な時間でした。

まさに成長期のベンチャー企業だったのですね。IPOに向けて、岡田さんはどのような役割を担っていたのでしょうか?

顧客向けのコンサルタント業務から始まり、営業企画、経営企画、法務など、本当に様々な部署を経験させてもらいました。四半期ごとに名刺のタイトルが変わるような時期もあってカオスでしたが、そのおかげで会社がどのように動いているのかという全体像を短い時間でも網羅的に学ぶことができたのはよかったです。労働環境としては非常に厳しかったのですが、そのスピードの中で多くのことを経験できたのは、今となっては貴重な財産です。
IPO後に退職。Googleへ

そして、その次がGoogleへの転職だったのですね。どういう経緯だったのでしょうか?

ベンチャーを退職した後、次に何をしようかと考えたのですが、自分は網羅的にいろいろな業務をやったつもりではあるけど、実際にはどれもレベルが低くて中途半端なので、できればもう少し強みだと胸を張れるような何かがほしいと思いました。英語は得意な方ではなかったのですが、前出の佐藤康夫さん(当時Google Japan セールスアンドオペレーション ダイレクター)にご相談したところ、そのままGoogleを受けることになったのがきっかけです。

すごい夢のあるお話ですね。

私が入社したのはセールスの部署だったのですが、過去の2社ではいろんな業務をつまみ食いしているだけだったこともあり、実は営業経験がほとんどありませんでした。周りは皆強烈な先輩ばかりという環境で、カルチャーもそれまでの日系企業とは大きく異なり、最初は戸惑うことばかりでした。

それは想像もつかないキャリアチェンジですね。

そうですね。ベンチャー企業のスピード感と、グローバル企業であるGoogleは全くの別物でした。ただ、企業内部のオペレーションを一通りやった経験は営業にも生きましたし、外資系のビジネスカルチャーや、異文化のコミュニケーションなど、新たな経験ができました。2度の転職を通じて振り幅のある職場を経験できたのは大きかったです。
第三章:成功の裏側で始まった葛藤。起業、M&A、そして故郷への回帰

Googleの後はどのような道を歩まれたのでしょうか?

Googleには5年ほど在籍し、退職したのは2011年の震災後ぐらいだったと思います。実は、以前から一緒に仕事をしていた杉原さんが、私より先にGoogleを辞めてアタラを設立していたんです。その杉原さんからお声がけいただきまして。ちょうどGoogleでの仕事も少し物足りなさを感じ始めていた時期でもあったんです。Googleでつまらなそうにしていた私を見て、杉原さんが声をかけてくれたという経緯もありました。それで、「請われれば一差し舞ってみよう(※)」という気持ちでアタラに参画しました。取締役として、チーム作りなど、色々なことに携わらせていただきました。
※この言葉は故:梅棹忠夫氏の言葉で岡田さんが大切にされている言葉だそうです。マーケティアのインタビューで岡田さんの仕事へのスタンスが存分に語られています。ぜひご覧ください。

なるほど。そこで私が知っている広告業界の岡田さんのキャリアがスタートするのですね。
華々しいキャリア。M&A、そして。

はい、そうです。ここからは少し複雑で、アタラの取締役をしながら2014年に広告代理店のアナグラムの社外取締役になりました。そしてアタラを退任して2017年には現在の自分の会社であるLIFTを立ち上げています。その後2018年にアナグラムと並行してSaaS企業のフィードフォースで社外取締役をすることになりました。

すごく華々しいキャリアです。アナグラムさんとフィードフォースさんといえば、2020年にはM&Aが成立したと記憶していますが、これは非常に稀有なご経験ではないでしょうか?

ええ、本当にたまたまなんですが、その時それぞれの会社に片足づつ突っ込んでいたので、縁があって両社の代表を引き合わせるという機会があり、協議を重ねた結果、M&Aという形になりました。まさか自分が役員を務める会社同士がM&Aをするとは、本当に想像もしていませんでした。

本当にジェットコースターのような展開ですね。そこまでされていたら、もう成功者なのですが、そんな多忙な日々を送られる中で、なぜ地方への移住を意識されるようになったのでしょうか?
いざ金沢へ

そうですね。M&Aも一段落し、2020年から2021年にかけては、フィードフォースグループの再編などもあり、妙に忙しい日々を送っていました。ただ、物理的にはあまり移動せず、自宅や個人事務所で仕事をするスタイルになっていました。そんな中で、妻が石川県出身であるというご縁があり、以前から漠然と地方への移住願望はあったので、エイヤと2022年に引っ越しました。

奥様のご出身地が石川県だったのですね。

はい。それにはコロナ禍で働き方が大きく変わったことが大きかったですね。どこにいても仕事ができるという感覚が強まりましたし、移動が減ったので満員電車に乗らなくても済む生活に慣れてしまったというのもあります。また、子供が生まれたことも、住む環境を考える上で大きなきっかけになりました。東京での慌ただしい生活よりも、もう少し落ち着いた環境で子育てをしたいという思いが強くなりました。どうせ会社に行かないのであれば、どこに住んでも変わらないのではないか、と思うようになったんです。

なるほど。様々な要因が重なって、石川県への移住を意識されるようになったのですね。

ええ。2021年には計画を立て、2022年の春に金沢へ引っ越しました(※)。まさか自分が東京を離れて地方で生活するとは、少し前までは想像もしていませんでした。
※このあたりのいきさつは岡田さんのnoteにも詳しく書かれています。
第四章:金沢から世界へ。情報格差を覆す岡田さんの視点

岡田さんが金沢に移住されてから、まもなく3年とのことですが、実際に生活されてみていかがでしょうか?また、東京を拠点としていた頃と仕事の面で変化はありましたか?

そうですね。金沢での生活は、私にとっては水が合っていると感じています。混雑も少なく、必要なものへのアクセスも良いので便利ですし、仕事に関しても、拠点を移したからといって大きく変わったことはありませんでした。移住後しばらくしてから仕事を整理して現在のLIFTに専念するようになりましたが、ありがたいことに今でも首都圏の企業さんとのお仕事も多く、地理的なハンディキャップはそれほど感じずに済んでいます。出張が増えがちなので身体は疲れますが(笑)

地方に移住すると、どうしても東京に比べて情報が入ってくるスピードや量に差が出るのではないかという懸念があると思いますが、技術的な情報やトレンドにおいて遅れを感じることはありますか?

それはよく聞かれる質問ですが、今のところ、実務にかんしてはそういった遅れは感じていません。私の仕事はインターネット関連なので、必要な情報はオンラインでほとんど手に入りますし、オフィシャルのドキュメントは常に公開されています。むしろ、誰かの解釈を経た情報よりも、一次ソースである公式ドキュメントを読むことの重要性を強く感じています。英語のドキュメントも多いですが、読めば済む話なので、情報やトレンドという意味では特に影響はないかなと思います。
日本全国も、世界中も、ほとんど二次情報

情報の一次ソースの重要性について、もう少し詳しくお聞かせいただけますか?

はい。あくまで実務についての話になりますが、多くの人は公式のヘルプやドキュメントを隅々まで読んでいるわけではありません。誰かが解釈した情報や、まとめられた記事などを参考にすることが多いと思います。しかし、特に技術的なことや最新のトレンドにおいては、公式の情報が最も正確で、かつ網羅的です。それをきちんと理解していれば、情報格差を感じることはないというのが私なりの経験則です。

なるほど。東京のアドバンテージとして、業界のコミュニティや横の繋がりなどを含めた「最先端」という点が挙げられると思い込んでいましたが、情報という観点でいうとおっしゃる通りかも知れません。

もちろん伝聞形式の情報は人間関係やコミュニティの重要性が非常に高いですし、都心のほうがつながりにおいて圧倒的に優位性があるのは事実ですが、私は人間関係がもともと狭いのであまり影響しないのかもしれません(笑)。もちろん、信頼できる人から直接話を聞くことや、難しい局面で互いに励まし合うことは非常に重要ですが、ノウハウの学習という点においては、地理的な差はそれほどないのではと考えています。
石川だからこそのメリット

逆に金沢に拠点を置くことで、何かメリットはありますか?

営業面でのわかりやすい利点は正直思いつきませんが、例えば採用において、金沢に限らず地方はどこも東京ほど同業他社が多くないので、自社の頑張りがそのまま地元の優秀な人材にとってのキャリアの選択肢の一つになり得るという側面はあると考えています。
もし、東京の会社と遜色ない仕事内容を提供できて、お客様と直接話せる環境を金沢で作ることができれば、それがそのまま地域の社会課題へのアンサーになりうるはずだと。ビジネスはつまるところ社会貢献ですし、地方には常に課題が山積みなので、ミッションやビジョンを無理やりひねり出さなくても、いい仕事が作れればそれがそのまま解決の糸口になる。四の五の言わずにとにかく頑張ればいいんです。何だか根性論みたいになってしまいましたが、経営者にとってはそれがメリットかもしれません。

地方にいながら、東京の企業とやり取りをする上で、工夫されている点はありますか?

そう言われると特にこれといった工夫はしていないです。。。インターネットがあれば、物理的な距離はほとんど関係ありませんので、むしろ、距離があるからこそ、無駄な移動が減り、お客さまに集中できるという側面もあるかもしれません。
第五章:「休むことは、遅れじゃない」金沢で見つけた持続可能な働き方

金沢に移って、生活の面で大きく変わったと感じることはありますか?

時間の流れに対する感覚は変わったかもしれません。以前は常に時間に追われていましたが、金沢ではもう少しゆったりと時間が流れているように感じます。仕事はそれなりに忙しいですが、プライベートとのメリハリがつけやすくなりました。

地方での暮らしの豊かさは、どのようなところに感じていますか?

金沢にかんして言えば、まず文化的な施設へのアクセスの良さですね。美術館や図書館などが充実していて混雑も少なく、平日にふと思い立って出かけることもできます。自然もすぐそばにあって、都市と自然のバランスがいいと感じます。以前は、あらかじめ計画していないと得られなかった経験へのアクセスがスムーズです。

価値観の変化もありましたか?

はい。以前はもう少しテンションを張っていた感じでしたが、現在はそれだけではない、いろんな振れ幅を許容できるようになった気がします。暮らしの質や家族との時間、地域とのつながりなどもそうですし、今は地方の生活こそがリアルなので、首都圏を相対的に捉えることができたのも一人の社会人として大きな変化だと思います。
最前線だからこそ、休息の重要さ

これまで非常に多忙なキャリアを歩まれてきたと思いますが、「休息」はどのように捉えていますか?

昔は「休む」という感覚がほとんどなかったです。特に最初の2社では土日も働き詰めで、Web業界では仕事に終わりがない。でも、それでは続かないと気づきました。肝臓の数値が悪化したり、睡眠不足が続いたりして、これはまずいと。家族ができたこともあり、意識的に休むようになりました。

「休むことは悪か?」という問いに対して、どうお考えですか?

決して悪ではありません。むしろ意識して取るべきものです。休むことでリフレッシュでき、結果的に仕事のパフォーマンスも上がります。金沢にいることで物理的に距離を取りやすくなり、オンとオフを切り替えられるようになったのも大きいですね。

情報の速さが重視されるWeb業界で、地方に拠点を移すことに不安はなかったですか?

ほとんどありませんでした。情報はインターネット上にありますし、むしろ余計なノイズが減って集中しやすくなった感覚があります。働くときは集中して働き、休むときはしっかり休む。その切り替えが今は自然にできています。
第六章:地方で最先端。岡田さんが描く、新しい価値創造の未来図

最後になるのですが、岡田さんは現在、金沢にお住まいで、東京の企業とも仕事をされていますが、東京一極集中という現状に対して、逆に地方にいるからこそのチャンスって何だと思われますか?

そうですね。私自身が東京を離れてみて強く感じるのは、地方には東京にはない魅力や可能性が眠っているということです。一歩地域に目を向けてみると、課題はもちろんありますが、それと共に優れた資産やチャンスもたくさんあります。

どのような課題や可能性があるとお考えですか?

まず地方の経済面の課題でいえば、ミドルティアの空洞化です。数でいえば大企業より未上場の中小企業の方が圧倒的に多いので、その分厚い中小企業群が豊かにならないと地域が豊かになりづらい構造がありますが、どうしても、大都市や大企業にあらゆるものが集中する構造があるので、世界を眺めても人口が都心に集中していくのは避けられないですよね。これは私の中でも大きなテーマになっています。

おっしゃる通りだと思います。資本主義の構造ですよね。

とはいえ、地方でも成長しているエリアはあるわけで、そこには必ず雇用の受け皿になっている産業があるんです。たとえば金沢では観光もありますし、近隣ではメーカーなどの企業を誘致して人口を増やしている市もあります。地方には長年の歴史や独自の技術、文化を持つ企業がたくさんあるものの、それだけで若い人を留めておくのはだんだん難しくなっているのも事実です。

観光業であれば飲食店などが盛んになりますが、サービス業は利益率が低いですし、環境の変化に影響を受けやすいですよね。伝統産業も雇用の受け皿としては心許ない。

そうなんです。だから付加価値が高い仕事を増えるとよいなと思っています。自分の得意なところでいえばマーケティングやコンサルなどはやりようによっては付加価値を上げやすく、物理的な距離も以前ほど大きな障壁にはなりません。もちろん雇用の創出はメーカーなどには遠く及びませんが、地方ならではの可能性がある分野の一つかなと考えています。
スローライフではない、最先端の経済的取組を東京との交流から

なるほど。発想の転換ですね。私も神戸にいますが、確かにむしろチャンスが多いような気がしてきました笑。

私自身、今からモノ作りはできませんし、やれることはWebテクノロジー関連なわけですけど、そういう仕事が少ない地方から、東京をはじめとした全国にお客さまが作れれば、地域の若者にもチャンスを作れるのではないかと考えています。実は我々のようなWebやテクノロジーの業界って地域の経済に少なからず貢献できるはずですし、東京と地方という二項対立ではなく、交流で仕事を生んでいければよいわけで。それが私のチャレンジですね。

地方というと、都会を離れたスローライフのような話しが多いのですが、まったくそうではないのですね。むしろ先進的な経済的チャレンジにみえます。

スローライフしたかったですが(笑)、可能性がありそうなのでせっかくならやってみようかなという感じです。まだ始めてみて間もないですが、今のところそんなに大きく外してはなさそうだという感触はあります。また、いろんな規模の会社を経験して思いますが、どの規模やフェーズが自分に合うかは健やかに生きるうえで割と重要な要素だなと感じます。私としては未上場のスタートアップや、成長しているスモールビジネスのほうが性に合っているので、そういう意味でも地域のミドルティアの経済に少しでも貢献するというのは面白いのかなと。

今日のお話しは、私にとっても目から鱗ですし、多くの人の希望になる気がします。そもそも株式上場やM&Aなどこれだけ多様な経験をもった人が、今、地方と東京の交流に可能性を見いだしていること。さらにはその岡田さんご自身がエリート街道を爆走されてきたわけではなく、むしろ試行錯誤の中で見つけてきた道だったこと。

自分としては、エリートどころか泥まみれという感じなので、そんなに価値のある話だとは思っていないのですが、丸山さんに面白がってもらえたなら嬉しいです。私から見ると神戸にお住まいの丸山さんの生き方こそ面白いと思っているので、ぜひまたいろいろお話ししたいですね。

ありがとうございます。ぜひまた金沢に遊びにいかせてください。
まとめ
岡田さんは、それこそ10年ほど前からお名前は存じ上げていたのですが、深くお話しするのは始めてでした。
勝手ながら、様々な経験をされた後、あがりのような形でスローライフやライフワークバランスの流れで金沢移住をされているのかと思っていたのですが、まったく違うお話しでした。
むしろ、いろいろな選択肢の中から、計画的でもあり、縁でもありというバランスで、一番面白い選択肢をとられた結果が金沢移住だったのだと。今回の一連のお話しは私にとっても目から鱗で、「地方だから最先端」「地方と東京との交流」はこれからの日本でとても面白い視点だと思いました。確かに、IT分野においては、誰もが海外の情報をおいかけている立場ですので、そこに地域の優劣はありません。
今回のお話しは、私も含め、多くの人にとって、改めて地方の魅力に気づくきっかけになるのではないかと思いました。
LIFTさんのブログは、そんな岡田さんの独自の考えも展開されていてとても面白いので、ぜひご覧ください。