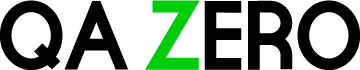大変お待たせいたしました。皆さんにもおなじみとなってきました一万文字インタビューです。
Cookieを使ったWebサイトのトラッキングがじわじわときつくなってきている話は、過去にもこのブログで何度か取り上げました。iOSに関してはITPなどの影響でとっくの昔にCookieを使ったトラッキングができなくなっています。トラッキングをテーマにアプリとWebの視点からMolocoの坂本さんと丸山が話をしました。
目次
開始直後に丸山が脱線しました…

今日は坂本さんと「アプリとWebのトラッキングと未来」というお題でお話したいと思います。
はじめに坂本さんのことをお聞きしたいのですが、技術に詳しそうに見えるので、元々はエンジニアだったんでしょうか?また、いつごろからアプリのトラッキングなどにかかわりだしたんでしょうか?

エンジニアにはずっと憧れてるのですが、残念ながらコードはほとんど書けません(笑)。僕がモバイルアプリの広告に関わり始めたのは、2011年にGoogleに中途で入社したときからですね。当時のアプリって大企業が本気で取り組み始めるよりもうちょっと手前で、個人開発者の方々がいっぱいアプリを作っていた時代だったんです。しかも、担当プロダクトは広告マネタイズで、SDKを実装してくださいって営業を主にしてた感じです。
そうすると当然、エラーが起きましたみたいな連絡がお客さんから直接くるわけです。僕から「バグが起きました」と社内のテック担当にそのまま持ってくと「簡単にバグっていうんじゃない!」みたいに怒られるんですよね(笑)。

あー

問題が再現する条件と再現しない条件、環境やバージョンなどの情報、とかをちゃんと切り分け整理してから持っていかないと、テックのリソースも限界があるから、全部を調べられないよとなるんです。
こんな感じでいわゆる、エンジニアやテクニカルサポートに近いところの仕事をセールスをしながらやらされてたというか、やらざるを得なかった状況が、僕の技術脳を作るのに貢献してくれたのかもしれないです。

ということは、切り分けで言うと、ある種の論理的思考みたいなところになっていくので、「多分こういうことが起こるんだろうな」みたいな勘所を習得されたというか経験されたと。

そうですね。対お客さんっていう意味でも対社内っていう意味でも、徐々に最適化していった感じです。ただ自分でコード書いて何か動かすところまではできないので、テックの人たちとちょっと会話できるぐらいにはなったというのが実情です。なのでエンジニア出身ではないんです。
==========ここから脱線==========

そういうことなんですね。
なんでお聞きしたかというと、たまに私がマーケティングのコンサルタントとして紹介されることがあったりはするんですけど、これが二律背反といいますか、エンジニア脳で考えてるときと、マーケティング脳で考えてるときでどうしても矛盾が生じるんですよ。

面白いですね。矛盾ってどういうことですか?

はい。なぜかはわからないんですけど、優先事項の判断基準が変わっていってしまうというか…。マーケットインとかプロダクトアウトとかって言うんですけど、どこで折り合いつけていいか自分でわかんなくなっちゃうみたいなことがあるんです。
なので反対意見というか似たような考え方を森野さんと一緒にやっていて、彼がいてくれることによって、僕はどっちかっていうとエンジニア脳に振り切れる。大体着地点が似ているんですよ。間違っているときには「間違っている」と言ってくれるし、最終的に「こういう考えだからこうなるよね」みたいな部分ですね。

いや~分かります。マーケとテックに限った話ではないかもしれないですけど、なにか物事を進めるときに、ある基準で判断するとAが最適解なんだけど、こっちの基準で判断するとBが最適解で、その間にグラデーションもあって、どうする?ってなりますよね。判断軸が複数あるというのがわかってないと、それこそ喧嘩しちゃったりみたいなとこあるじゃないですか。

ありますね。
そこで、あんたの言うこともわかるんだけど、と相手が理解できる人どうしで会話すれば、もうちょっと円満に着地できるというか。

とりあえず落とし所を探れますよね。
今の丸山さんのお話で、マーケ脳とエンジニア脳が両方頭の中にあって、どっちも行き来できるっていうのは、自分の中で二つの視点持てているってすごくいいことなんだろうなと思います。

でも、自己矛盾で苦しむんで、あんまりよくないかなと思うことはあります。だんだん自分がわかんなくなるっていうか…。
坂本さんにインタビューさせていただく前に、YouTubeチャンネルでのクラシコムの青木さんの動画を拝見したんですよ。すごい面白かったですし、あの人も本当に哲学者というかあんなに割り切った自然思想みたいなのを持ってる人すごいなって。
※森野コメント
坂本さんは坂本達夫のスタートアップ酒場!!というYouTubeチャンネルをお持ちで、その中でクラシコムの青木さんと対談されています。とても面白いので見てみてください。
- 【北欧、暮らしの道具店】ビッグゲストに普段メディアでは聞かないアレコレ聞いちゃいます(ゲスト:クラシコム社長 青木耕平氏)1/3 – YouTube
- 【北欧、暮らしの道具店】社運はかけない、リスクは取らない!?普段は聞けない独自の経営論を深堀り??(ゲスト:クラシコム社長 青木耕平氏)2/3 – YouTube
- 【北欧、暮らしの道具店】『不動力』で乗り切る今の時代のブランド価値のリスクマネジメント。語られなかった承継について。(ゲスト:クラシコム社長 青木耕平氏)3/3 – YouTube

抽象化してるし視点も独特ですよね。

坂本さんが動画の中で「それって下のメンバーはすごい大変ですよね」っていうお話を出されたときに、本当その通りだろうなと思いまして。独特だから着地点とか経営思想がはっきりし過ぎるのが良さでもあり、みんなの全体調和の合意みたいなところに達しなそうな気もしていて、先ほどの私の自己矛盾も解決するのかなと。
いきなり全然違う話になっちゃったんですけど。

こういう話はこういう話で大好きなんですけども、永遠に本題に行かないので(笑)。
==========脱線ここまで==========
ITP後のアプリ業界で何が起きたのか?

…はい。
早速なんですけれども、メインのお話としてはまさにトラッキングのことでして著書も拝読しました。その中で、大きく分けて二つのテーマについて、今日お話をお聞きしたいと思っています。
1つ目のテーマはトラッキングで個人のターゲティングをすれば精度が上がるという世界がある一方で、カウンターカルチャー的にプライバシーみたいのが出てきています。この状況で広告の未来像がどうなっていきそうなのか。2つ目は、その話があったうえで、日本がどうなっていくのか?ということです。

了解しました。雑談からうってかわって、本題めちゃ重厚ですね。

日本では影響力を持つiOSが個人トラッキングをどんどんNOにしていったときに、アプリ業界で起こってたことってどんな感じなんですか。ざっくりしちゃってますけど。

端的に言うと、業界激震だったし、今もずっと余震が起きてるみたいな感じではあります。テクニカルな面では、トラフィックのほとんどでIDによるターゲティング・トラッキングが効かなくなってしまいました。

iOSは本当に駄目になっちゃったんですね。

アプリ新規で開いたときに、このアプリに何々をトラッキングを許可しますか?というのが表示されますよね。これで『許可』を押す人の割合が3割ほどだ、という調査が出ています。

WebサイトでCookie許可を押す人も3割ぐらいなんですよね。

そうなんですね!同じ3割の人が許可してるのか、全ての人が気分で3回に1回ぐらいランダムに許可してるのか、どっちなんだろうと気になります。アプリではどうやらランダムらしいというデータも出ています。
この3割がなぜ困るかというと、トラッキング可能なトラフィックは実際には1割未満になってしまうからです。例えば、ECサイトのアプリが広告主で、乗換案内のアプリに広告を出したとします。IDによって端末レベルまでトラッキングしようと思うと、広告を見ている乗換案内アプリでも許可してもらわないといけないですし、広告経由でインストールして起動したECサイトのアプリでも許可してもらわないといけない。そうすると3割×3割で9%しかトラッキングできないとなるんです。

確かにそうですね。

こういった追跡型の広告を制限することをLAT(Limit Ad Tracking)と呼んでいて、弊社の広告で発生しているアプリのインストールのうち8~9割ほどがLATから発生しています。裏を返すと、トラッキングできる人の割合が1~2割ということなので、調査データと近しいものとなるんですよね。
これがもし、同じ3割の人が常にオプトインするのであれば、3割のインストールがトラッキングIDで判別できてるはずなのですが、そういうわけでもない。ですから、人は概ねランダムに許可するかしないかを判断しているようです。
Molocoさんはどんな会社?

面白いですね~。
ここまで話していただいておいてから申し訳ないのですが、Molocoさんのサービスがどのようなものかを教えていただけますか?ここがわかると話もわかりやすくなると思いますので。
※森野コメント
脱線せずに最初にサービスを聞いてほしかったです。

僕たちは機械学習の会社ですっていうふうに言っています。Googleをはじめとしたウォールドガーデンと呼ばれる企業に対するカウンターとしてやってるイメージですね。
GoogleやFacebookに広告を出稿しているときには、彼らが開発した最高峰の機械学習技術の恩恵を受けられているんですけど、それ以外の数多あるアプリ群、いわゆるオープンインターネットと呼ばれる部分に関しては、機械学習技術を自分たちだけで磨くことはできないです。その一方で、ファーストパーティーデータでは彼らの方が質の良いデータを持っている。例えばフードデリバリーアプリは、だれがいつ何を注文しているかなどがわかっているはずですよね。しかし、ビッグテック企業と同じ水準でマネタイズすることができていない。会社規模で見るとGoogleやFacebookほど大きくないから、技術投資ができてないからだと思っているんですよね。
そこで僕らがGoogleとかFacebookに負けないぐらいの良い機械学習の技術を作って、マネタイズやプロモーションの支援をしているんです。
坂本達夫さんのプロフィール
Business Development, Supply
Moloco楽天、Google、AppLovin、Smartly.ioを経て、2021年よりモバイル事業者向け機械学習マーケティング企業であるMolocoの日本事業の統括に就任。2023年末より現職。モバイル広告・マーケティングテクノロジーの専門家。国内中心に約80社のスタートアップにエンジェル投資を行う。東京大学経済学部卒業。福岡出身、関西育ち。2児の父。著書『アプリマーケティングの教科書』

UberEatsだったりとか、Airbnbのようなある程度のインストール数があるアプリを作っている人たち、つまりファーストパーティーデータを持った人たちが、自分たちのアプリをメディアと捉えて広告収入を得るような仕組みみたいなイメージですか?リテールメディア的な。

最近ではそういったこともしていますが、元々のメインの事業はアプリに特化したDSPですね。
結局のところ広告は、広告主さんのサービスと、潜在的にそれを使う可能性があるけどまだ使ってないユーザーをマッチングさせる技術です。そのマッチングのさせ方が各社で違っていて、例えばGoogleの検索連動型広告だったらキーワードで、Meta広告だと年齢性別とか趣味趣向のようなデモグラや個人に関するデータでマッチングさせています。僕らはそれをアプリのファーストパーティーデータで、かつ個人情報に該当しないもの使ってやろうとしているんです。
アプリのトラフィックには90個ぐらいシグナル、例えばIPアドレスとか端末のタイプ、iOS・AndroidなどのOSとバージョンなど、が含まれています。既にダウンロードされているアプリのデータを見れば、例えばiOS15系の人と16系の人だと16系使ってる人の方が20%ぐらいLTVが高いよね、みたいなことがわかるはずです。そうなると、16系の人のトラフィックを広告で買うときは、15系のトラフィックに入札するよりも20%高く入札してもいいはずだよね、ってなりますよね。

なりますね。

たくさんあるシグナルの中でどれが一番重要なのかを見つけたり、どれがどれぐらい重要なのかの重み付けをするのは、人力ではとてもできないので、弊社がデータをお預かりして、自分たちの機械学習にかけて計算しています。その上で、GoogleやMetaとかではない配信先のトラフィックを買うときに、このインプレッションはいくらで買おう、この広告主さんだったらこれぐらいの値づけが妥当なはずだよね、といった判断もしています。

今、お聞きしてWebの未来だなと思いまして、Webに関しては日本国内ではまだまだCookieがOKなので個人が追えるんですよね。それもいつまでかはわからないので、すでにそうなってしまっているアプリの世界が参考になります。
アプリの世界とWebの世界の現状

Web世界ではGoogleがサードパーティーCookie廃止をまた延期しますと言っていますが、Cookieって実際にはどれぐらい使える状態なんですか?海外のように厳しいところだとアプリのポップアップとかと同じで、ウェブサイトにアクセスしたときに「許可します・しません」みたいな表示しないと罰則がありますので、既にCookieが結構取れなくなってきちゃってるみたいな感じなんですか?

こちらの記事にあるように海外というか欧州ではほとんど取れなくなっていまして、かろうじてアジアだけが残っている感じですね。そんな状態ですからGA4などCookieを使って計測するのはもうダメだとなっていて、CRM偏重になっているんですよね。とにかく登録してもらってファーストパーティデータ取れば、許可を得た人にだったらCookieもセットできるから自分たちからアプローチできるという流れです。

WebはCookieがユーザー獲得のところであったり、ユーザーになった人たちのサイトの利用状況を分析したり、リターゲティング広告で離脱したユーザー再訪させたりとか、いろんな用途で使われていますよね。CRMで言うと、一度ユーザーになった人に対して、継続的にコンタクトを取り続けるところは有効かなって思うんですけど、一方で新規のユーザー獲得がうまくトラッキングできないところに関しては、全く解決にならないですよね。

おっしゃる通りです。新規のユーザー獲得には全く使えないのですが、先を行っているアプリではどのようにしているんですか?

アプリの世界ってIDFAが取れなくなりました。iOSだとSKAdNetwork(※)をAppleが用意してきたけど、過渡期なので今はいろいろ足りてないことがあるからマーケターとしては使いにくくて、AdjustやAppsFlyersみたいな広告トラッキングツールが提供している確率論モデリングみたいなものを使っています。
簡単に言うと、いろんなシグナルを統計的に分析して、この広告に接触したユーザーと、このインストールは、シグナルが50個あるうち40個ぐらいが一致してるから、この広告の成果を紐付けてOKでしょうみたいなものです。トラッキングツール曰く、95%以上ぐらいは推定モデルでトラッキングができているはずだということです。完全にできないことは、いわゆるリターゲティング・リエンゲージメントのような分野で、これはIDがないとどうしようもないですから。
※参考URL:SKAdNetworkとは何でしょうか?どのように機能するのでしょうか? | Adjust

計測できている部分がほとんどないんですね。
私の知り合いでグローバル企業で広報系の仕事をしている人は職が危ないと言ってました。今まではブランディングに費用をかけて潜在顧客にリーチして、その人たちがどう来てるかという部分が数値計測ができてレポートにしていました。これを報告することによって、明確なコンバージョンではないかもしれないけれども、会社としては価値があるという判断をしてもらっていたのが計測できなくなっちゃうわけですから、

効果があるからこれをやり続けましょうと、根拠とともに言えなくなってきてるってことですよね。
計測できないからと言って新規顧客獲得の広告を止めるのか?

売上偏重に行こうと思えば、1人当たりの売上どこまで上げるかという短期利益に走るかもしれないですけど、これって短期の刈り取りにもなりかねないと思うんです。

この流れはめちゃくちゃ面白いです。
例えばテレビCMに1億、YouTube広告に5000万円使って、実施前後でユーザーがこれぐらい増えました、って状況だったとします。それぞれの効果って明確にトラッキングできないじゃないですか。じゃあテレビCMを止めるかというと、止めない。成長が止まってしまうから。広告の効果が厳密に計測出来なくなったから止める、ってのは本来やるべき行為ではないんですよ。おそらくデジタル広告がこれまでトラッキングできたことの功罪でいうと、罪の方がすごい働いていると思ってます。本当は見えないだけで効果があるのかもしれないけど、数字が取れないとなった瞬間に「わからないからやらない」となってるということですよね。

そういう感じになっているんだと思います。ネガティブモードになっているというか。

さっきCRM偏重になってるって話をされてましたけど、既存のユーザーでデータ利用の許諾が取れているユーザーに対しては、トラッキングができるから、マーケターの時間とか予算が寄っている感じなんですね。CRM自体が僕は悪いものではないと思うんですけど。

そんなことおっしゃってました。予算がそっちの方にばかり流れ始めてると。まさに罪の方ですよね。
ところが面白いことに、デパートで働いていて実際にお客さんと接している人にはそんな馬鹿な話あるかって言われまして。デパートで働いている人はCRMと『目の前の通りを歩いてる人たちへのアピール』とは分けて考えているんですよね。なので『潜在顧客を取りに行かない』という考え方自体がどれだけきついことになっていくのかが肌感覚でわかっているんですよ。自分のところに来た人”だけ”を接客するって『死への道』だよって。

そうですよね。元々オフラインでやってるビジネスとか、テレビCMやポスティングなどのオフライン広告は、100%のトラッキングができない前提のもとで成り立っていて。それでもなんとか取れるデータや、現実の観察などから、何かしらのフィードバックを得てやり続けていますよね。
トラッキングはできないんだけど、チラシ見てきたよ!みたいな人がたくさんいるという肌感とか、卵を98円にしたときと118円にしたときとの来客数の違いみたいなのとか。

まさにそうだと思います。

厳密な意味ではテストできてないんだけど、これは意味があるこれは意味がないよねというのを積み上げて、四苦八苦して頑張ってきた人たちから見ると、『トラッキングできないから集客にお金かけられない』なんて「甘いこと言うな!」ってなりますよね。既存ももちろん大事にするんだけど、それだけやってたらシュリンクしていっちゃうから、新規も枯らさないように頑張らないといけないわけですから。

まさにそういうお話で、究極のとこを突き詰めると、冒頭でお話した青木さんが1つの答えを出していると思うんです。小売って最終的に『ブランド価値の利回り』だということをおっしゃっていましたので。それなのにトラッキングしすぎのせいでブランド価値を毀損する方に走っていくこともあって、ポップアップを出してユーザー登録しませんかしませんかってやってしまうと思うんですよ。肌感覚でやったらやらなくてもいいようなことを、やっていくような流れになるかもしれないですね。
あとはトラッキングというか計測でいうとGA4に頼っていいのかという問題もあります。GoogleがGoogle 広告を持っていてその会社がGA4という計測ツールも提供している。広告と計測の両方を持っていたら、うがった見方ですがどうにでもできちゃいますよね。
広告媒体とトラッキングをわけて効果を公平に判断できるのか?

アプリの世界では、AdjustやAppsFlyersのようにトラッキング事業者が強かったというか、アプリ用のGoogleアナリティクスとかFirebaseが広告トラッキングで覇権を取ることはまだできていません。その中で、審判とプレイヤーとを本当に分けて公平にできるの?という議論があります。公平性の観点からも、ストライクとボールの判定をするのは、広告プレーヤーではない人たちがやった方がいいよねということは、トラッキングツール事業者が主張していて、自分も実際そうだとは思うんです。
過去はトラッキングツールとGoogleなどの巨大広告媒体との力関係でいうと広告媒体の方が強かったです。例えば外資系のある広告トラッキングツールで、何らかの事情でFacebook広告がトラッキングできなくなりました。FacebookからBANされたということですね。そういうことが起きると、そのトラッキングツールって使いづらいよねっていうことでユーザーからの信用をなくして、シェアをどんどん落としていったことがあるので、トラッキングツールとしても巨大媒体とは仲良くしなきゃいけないよねみたいな。

パワーバランスがあるということですね。

トラッキングツールを使って広告の計測をするときは、通常はトラッキングツールが最初に成果の判定をして、その成果のデータを媒体に「あなたのところの成果はこれだけでしたよ」とフィードバックするようになっています。Molocoもそうです。
これが巨大媒体だと、「先にこれがうちの広告経由で取ったユーザーだ」みたいなデータを出してから、トラッキングツールに投げます。今度はツール側で、「そう言ってもこのユーザーとこのユーザーは、あなたの広告に接触した後で他の広告と接触してるから、ラストクリックだとこれは対象外だね」と消します。残りがあなたの成果です、って返すんです。第三者判断はあるもののブラックボックスになっていて、僕らみたいな巨大ではない広告媒体との間では力の差がずっとあったんですよね。

はい。

これがApple先生のSKAdNetworkによって、格差はなくなりました。なぜならAppleが唯一の絶対神だからだ、みたいな世界になったからです。

なるほど!

とはいえ、Apple Search Adsという広告媒体を持っていて、これが自分たちで審判のツールを作ってしまっていて、しかもその裏側は超絶ブラックボックスなんですけど…。これがGA4とGoogle 広告の関係に似てるなと。

確かに、まさにおっしゃったように、アプリの方がiOSの影響がより大きいですから先行している感じがありますね。

Webの世界ではChromeでのサードパーティーCookieの廃止が実行されていなくて、アプリはそれがAppleによって実行されちゃったんで、世界の半分ぐらいは厚い暗闇に覆われています、という状況に先になってしまった感じがしますね。

ありがとうございます。すごく適切なイメージしやすい例えです。そうなると何が起こるかっていうのがわかりやすいです。
あとはユーザーからしても、広告主からしても結局どうなるの?が気になると思うんですよね。こうなるからこれやっといた方がいいよ、というものはありますか?
世界の流れを見て専門家と議論することで将来が見えてくる

今後50年みたいな長いスパンで見ればわからないですが、5~10年といった短いスパンでは、個人データが今よりも自由に使えるようになる方向に世界は動かないと思った方がいいですね。これはテクニカルな話というよりは、アメリカとヨーロッパと中国といった大きいレベルの政治的な話なので、プライバシーがよりきつくなる方向には行くだろうなと思っています。
この前提で会社の業績を伸ばし続けることを義務付けられている立場の人だったとしたら、Cookieが取れます、広告のトラッキングができますといった前提条件が高確率で崩れるので、崩れたときにどうやって伸ばすんだっけ?というのを、ゼロベースで考える必要があるのかなと。何というか、『それがあなたの仕事でしょ』っていう感覚ですね。

その時は坂本さんの著書を読んだらいいです、となりますね。ある程度はこういったことをやったらいいよと書かれていますので。

まず現状認識を正しくするっていう意味で、自分の本とか丸山さんの記事などをベースに、今どうなってるのかっていうのを正しく知る。かつ、もう海外で問題が起きているので、次に日本で何が起こるかは想像がつくはずです。
そこを勉強した上で、この想像というか仮説の精度を上げるために、いろんな人とディスカッションをして仮説をぶつけて、前提や思考のプロセスがあってるの?何か落とし穴がないの?を議論することが意義があると思っています。丸山さんのようにCookieレスの計測ツールなどを提供している人たちに、時間的な面でも金銭面でもリソースを割いて、自分の仮説をアップデートすることなのではないのでしょうか。

おススメしていただいて嬉しいのですが、ここで時間になってしまったので続きは次回にしたいと思います。そのときは、我々のツールでもいろんなデータが出ていると思いますので。

はい、ありがとうございました!
既にCookieでのトラッキングができなくなってしまったiOSの世界では、機械学習を使って成果を判断していたんですね。これはどう考えてもWebの世界にもやってきそうなので、今後はこの手のサービスが増えてきそうですし、そういった動きにも注目しないといけないです。しばらく先の未来が見えればやることもわかってくるので、坂本さんがおっしゃったように識者の方の意見をチェックしないといけないのと、議論して理解を深めるのが大切になってきそうですね。
ということで、丸山さんにもうちょっとインタビューがうまくなってほしいと思ったのでした。
執筆:運営堂の森野